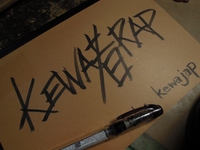想像してごらん、とジョンは歌ったけれど

これくらいの加工ならば彼女たちにも差し障りない...かと思いますがいかがでしょうか
「まだあるスナップ集シリーズ」より...ってどんなシリーズやねん、って感じですがこれは傍目には開演前の穏やかな時間
とはいえ、メイク中なのでむしろ気合が入っているんでしょうけれど(普段)メイクをしない男どもにとっては何だか神々しささえ感じるから不思議なものですが
さて
立春後だというのにまだまだ冬が立ち去る様子もない今日この頃ですがいかがお過ごしでしょうか
「次回作に向けて」などと勢い宣言してみたはいいけれど、そう簡単に書けないのがホンというものでして
次のホンの為のリサーチ...なんて聞こえはいいけど実の所調べたり読んだりした、からといってどうにかなるものじゃないんですよね
資料だけ、知識だけ揃えばどうにかなるなら「想像力」などというものは必要ないわけで、かの小さん師匠(言うまでもなく先代の柳家小さん師匠の事です)がおっしゃった「狸の心持ちになってみろ」という名言も「想像するしかない落語の世界の住人」を演じるにあたって必要だからこそ
そうでなくとも「演じる」という作業は、動物、屍、ゾンビ、殺し屋、侍、ガイジン、異性、異星人、年齢...と挙げたらキリがないほどの役割だけでなく、時代、地域、星、とそれこそ言ったもん勝ち、やったもん勝ち、とばかりに何でもアリなわけです
そこは「創作」という「想像力」プラスな要素が加わって、なのですが誰もわからない時代や地域のことならば「創作」で片付けられるわけですが誰もが知っている事実、となるとそうもいかないわけです
なのでやっぱり出来る限りそのことについて調べる...という作業になるのですがモノには限度がありましてね
だからそれを補うのが「想像力」という事になるわけです
とはいえ、ほんとのところその現場、その時の空気感とかそういったものは実際にその場所、その時代に居合わせた人でないとわからないわけで、決して「当事者」になどなれるはずもなく
どう頑張ったってせいぜいが「代弁者」もしくは「傍観者」
精一杯演じてみたところでリアルさには程遠い
ならばその時その場所に居なければ絶対に無理、なのかと言ってしまうと何も創れない、何も始まらないわけです
だから割り切るしかない
割り切って、そこから自分が出来る事を考えそれを精一杯やる
そこからは資料もウィキペディアも役に立たない、微々たるとしても自分の中の想像力をフルに駆使し、それを繰り返すことによって自分の体験としていく
それが「稽古」というもの、なのかもしれません
...なんだかエラそうなことを勢い書いてしまいましたがそれとてお客さんの前ではそのまま有効かというとこれが面白いモノでして
ライブだからこその空気感というんでしょうか
観ているお客さんも常に受け身ではなく、自然と想像力を使うわけで、そこである種のケミストリーが生じる
つまり「ライブ」として成立したか「発表会」で終わったか、は演者と観客の関係性、想像力vs想像力によるもの
といっても過言ではない
...んじゃないかな、と
思ってみたのですが何よりもまずはベースになるものを何とかしないと、ですね、はい
とりあえず資料から...
ってまた戻ってるし
m(__)m